【人権フォーラム】久間泰弘さんインタビュー「俟つこと。命と人権は不可分であること。」
人権擁護活動に取り組む宗門僧侶の方々へのインタビュー第3回は、曹洞宗人権教育啓発相談員を務める久間泰弘さんにお話しいただきました。

ご自身も被災された東日本大震災発災後は、災害復興支援活動に従事する一方、大規模災害・社会の急速な変化の中で不安や悩みを抱える子どもたちの心の声を聴く電話窓口「チャイルドラインふくしま」の開設に尽力し、第40回正力松太郎賞青年奨励賞も受賞されました。
「俟つ」という姿勢。それは、人権問題を考える上で欠かすことのできない、重要なキーワードです。「俟つ」という言葉には、何もせず「待つ」のではなく、希望を抱いて時を過ごすという意味が込められています。
この「俟つ」という姿勢を軸に、震災、そして人権問題の本質に迫ります。
久間泰弘さん プロフィール
曹洞宗龍徳寺住職。全国曹洞宗青年会では、16期広報委員長、17期副会長、18期会長(平成21年5月~平成23年5月)、19期顧問を歴任。曹洞宗東日本大震災災害対策本部復興支援室分室主事。他
『俟つ』という姿勢
―まず「人権」にまつわる活動に取り組むきっかけから教えてください。
久間:私自身が主体的に取り組むようになったのは、宗務所の人権擁護推進委員に任命されたり、全国曹洞宗青年会の広報委員会に参加させていただくようになってからです。その活動の中で、早稲田大学の喜多明人先生から「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」について研修を受けていたことが、私にとって大きな転換点となりました。
―「子どもの権利条約」と言いますと、18歳未満を子どもと定義して、権利をもつ主体として子どもを位置づけた国際条約ですよね?

久間:1989年に国連で採択された国際条約です。比較的歴史が浅いにもかかわらず、多くの国と地域が締結しています。私がこの条約を知ったのは大人になってからなのですが、その大人と同様にひとりの人間としての人権を認め、子どもならではの権利も定めた理念と内容は、学生時代に出会っていたら、随分と人生が変わっていただろうなと思っています。
―どのように変わっていたと思いますか?
久間:この条約をきちんと学ぶことで、自分を含めて多くの人が自分の人生を主体的に受け止められるのではないかと思えました。その衝撃を受けたままに人権にまつわる活動が始まり、今も続いています。
―具体的にどのような点に衝撃を受けたか、教えていただけますか?
久間:「俟つ」という姿勢ですね。相手の方の全人格を受容し、考え、発言を俟つ。実際に「子どもの権利条約」について学ぶ研修会では、受講者それぞれが本音を語り始めるまで徹底的に時間をかけていました。とにかく、時間が足りないと感じるほどの研修会でした。それがまさに、相手を受容し、俟つという姿勢を体験できた、貴重な機会でした。
―俟つ姿勢のどういった点に衝撃を受けたんですか?
久間:誤解を恐れずに言えば、様々な面での格差が拡がったといわれる2000年代以降の日本では、ある意味では「言ったもの勝ち」の世界になってしまった印象があります。つまり、相手の声や状況を配慮することよりも、自分の利益のみが最優先されるようになってしまった。また、子どもの権利実現を語る上で、しばしば問題になるものに「子どもは大人を言うことに従っていればよいのだ」という発言があります。これは、その大人が“子どもとは何ら話し合うつもりがない”という態度や人間性を現しています。このような時代背景の中、「俟つ」という姿勢に私は衝撃を受けたわけです。相手に何かを付け加えるのではなく、相手の気づきをひたすらに「俟つ」というのは、非常に禅的なアプローチにも感じました。
―確かにそうですね。
人権とは個々人の生活と不可分である
―久間さんは、東日本大震災の震災当事者としても復興活動に従事してきました。
久間:はい。人権擁護推進本部と関わらせていただいているのも、震災活動をしていたことが大きいと思います。私にとっては人権との関わりを振り返ることは、震災を含めた個人的なことが多く影響しているんですよ。
―復興活動と人権問題って、どのような関係があるのでしょうか?
久間:ご質問には、「人権」を社会的な問題として個別に捉えているという前提があるかと思います。そもそも人権を、個々人の生活と切り離して考えること自体が違うと思っています。人権とは、人間そのものであり、本来不可分な権利です。ですから、災害と人権問題も、分けて考えるべきではないと思います。
―なるほど。被災者のそれぞれに人権があるからこそ、すべての活動は人権問題でもあるということですね。
久間:復興の問題と人権問題を個別の問題として捉えてしまう背景には、報道の影響も大きいと感じています。現代の報道は、損害を受けた状況や事象ばかりを取り上げがちです。「泥を見ずに人を見る」という言葉があるように、現地の人々が何を考え、苦しみ、復興に向かおうとしているのか、といった精神的な部分を伝えていくことが大切です。本来は事実と感情の両面から、バランスの良い情報を得ていく必要があると思います。
―なるほど。

久間:人間は感情の生き物ですから、人の声を聞いていくことはとても大事です。どのような事実があり、どのような意見や気持ちがあったのか。一つひとつ声を聞き、アドボカシー(権利擁護の主張のこと)をしていくしかない。曹洞宗の人権学習でも実践していることです。
―では、あらためて被災地の活動で大事にしていることを教えてください。
久間:被災地での活動に限らず、人権の見地からいいますと「相手に同化しない」ということを大事にしています。相手の苦しみや悲しみに近づき、自分ごととして捉えはしても、相手の人生文脈へ乗り込むような同化はしない。これが人権活動において大事なのではないでしょうか。
―具体的にはどのような行動を心がけているんですか?
久間:例を出すと、仮設住宅で被害者の方とお話しするときに「わかった」「わかります」と簡単に同意してしまいそうになりますが、その一言でさえ相手を傷つけてしまうことがある。そういった配慮・弁えを忘れないよう心がけています。
―東日本大震災の復興については、どの程度進んでいるのでしょう。
久間:今は直接支援の現場からは離れておりますので、すべて把握しているわけではないことを前提にお話しします。今年(2025年)の3月11日で14年目を迎えますが、未だに復興の青写真を描けず、手探りで進めているような状況です。特に福島は、その土地に住み続けることが可能なのか、これから判断をしていかないといけません。考え方も人それぞれで、中には、日々生きることだけを考えておられる方もいらっしゃいます。
―なかなか「復興した」とは言い難い状況なんですね。
久間:復興にはゴールがありません。年数や場所で区切って語ることはできないのです。阪神・淡路大震災の17回忌に参列した際、地元の方々が16年経っても号泣されていた姿に、不慮の災害で受けた悲しみ・苦しみの深さを再認識しました。
以来、復興のゴールを設けることは慎み、ずっと続く悲しみや苦しみに少しでも寄り添うことこそ、宗教者としての命題だと、私自身も心に刻んでいます。一人ひとりが「これがゴールだ」とおっしゃるなら、それがそうであると考えています。
人権は、自己省察のきっかけでもある
―宗教というのは個人の精神を支えるものであって、人権とは関係ないと考えられる宗教者も多いと思います。
久間:先ほどお話したように、やはり人権と個人を切り離して考えているからではないでしょうか。「人権」は誰にでも備わる当然の権利と教わります。しかし、そう捉えた瞬間に、自分とは何か関係のない―自分とは別の誰かが何とかしてくれる
―別の概念に感じてしまう面もあるのではないでしょうか。世間では当たり前なので、当たり前に持っているのだと錯覚してしまうのではないかと。
―そもそも不可分なものであると捉えるべきなのかもしれませんね。
久間:人権問題というのはとにかく、自分自身であり、人間自身、個々人それぞれの問題であるというところから考えないと、必ず道を外してしまいます。
例えば、「子どもの権利条約」について日本の国会答弁で「子どもの人権侵害の問題は発展途上国の問題だ。だから日本では新しい立法は不要である」と発言されたことがあります。今では信じられませんよね。
―ああ。捉え方を間違えていると、集団であっても道を外してしまう。
久間:ニュアンスは難しいですが、ソーシャルな問題であるからこそ、語る際はパーソナルに語る。そういった捉え方が必要だと思います。ですから、宗教がパーソナルなものであることは否定しませんが「人権と関係ない」と捉えるのは、そもそもおかしなことだと思います。
―「人権問題」と一口に言っても、人種やジェンダー、社会的な格差など、非常に多様な問題が内包されていますよね。このような状況をどう捉えていけばいいとお考えですか?
久間:おっしゃるように、人権問題の切り口は急速かつ広範に広がっています。それらを網羅することは難しいですが、少し注意を向けていくことから始めると良いと思います。我々相談員の中では、専門分野を持ち寄り、知識を深めるようにしています。
―なるほど。個人としては、どのように捉えるといいのでしょうか?
久間:まずは、自分自身がどのような苦しみや悩みを抱えてきたのかを振り返ることが、個別多様な人権問題へのアプローチにつながるのではないでしょうか。私自身も宗教者として自己省察を非常に大事にしています。
日々、自分自身の喜怒哀楽を丁寧に振り返り、正していく。そういった視点がなければ、他者に寄り添ったり、何かを届けることはできないのではないかと思います。
―自分自身にも不可分な人権があるわけですから、自己省察から学ぶことは多いのかもしれませんね。
久間:人権問題は、自己変革を促すきっかけでもあります。自分自身を批判することでもあり、成長を促すものです。一人の人権・自分自身のためにも、一つひとつ解決を目指して学び、歩むことが大事だと思います。
**************************************************************************************************
人権を学ぶ推薦図書―③
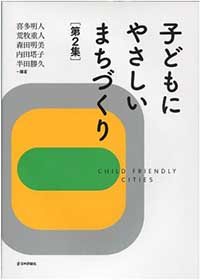
『子どもにやさしいまちづくり―自治体子ども施策の現在とこれから』喜多明人・荒牧重人・森田明美・内田塔子―編著/日本評論社発行
子どもの権利条約を日本国が批准して10年目に刊行された著作。現在の都道府県自治体における子ども施策の基本型が示されており、この20年で子どもの権利実現への視点や環境がどのように変容してきたのかをあらためて知ることができる一冊。



